飲食店の現場で日々忙しく働く皆さん、電話対応はどのように行っていますか。お店にかかってくる電話は、お客様との最初の接点となることが多い重要なコミュニケーションです。予約の受付から、メニューやアクセスに関する問い合わせ、時には予期せぬご意見まで、その内容は多岐にわたります。この電話対応一つで、お店の印象が大きく左右され、売上や評判に直結することも少なくありません。特に、丁寧でスムーズな対応は、お客様に安心感を与え、来店への期待を高めます。逆に、少しでも不手際があれば、お客様は不安を感じ、予約を取りやめたり、悪い口コミにつながったりする可能性も潜んでいます。
この記事では、飲食店スタッフなら必ず押さえておきたい電話対応の基本から、クレームを未然に防ぎ、顧客満足度を高めるための具体的なノウハウまで、実践的な「極意」を分かりやすく解説します。日々の業務にすぐに活かせるヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。
電話対応がお店の印象を左右する理由
第一印象としての電話の声と話し方
電話応対における「声」は、お客様が受け取る第一印象の大部分を占めます。対面とは異なり、表情や身振りが見えないため、声のトーン、話すスピード、言葉遣いがより重要になります。明るく、聞き取りやすい声で、丁寧な言葉遣いを心がけることは基本中の基本です。例えば、「はい、レストラン〇〇でございます」という第一声。この声が明るくハキハキしていれば、お客様は「歓迎されている」「安心して話せる」と感じるでしょう。逆に、低くボソボソとした声や、不機嫌そうなトーンであれば、「忙しいのかな」「電話して迷惑だったかな」とお客様を不安にさせてしまいます。
具体例を挙げましょう。ある人気イタリアンレストランでは、予約の電話がひっきりなしにかかってきます。忙しい時間帯だと、つい早口になったり、声のトーンが低くなりがちですが、そこのスタッフは「少し高めの明るいトーン」を意識し、「お電話ありがとうございます。レストラン〇〇、〇〇が承ります」と、必ず名乗ることを徹底しています。この最初の数秒で、お客様は「ちゃんとしたお店だな」という印象を持つことができます。また、話すスピードも大切です。早口すぎると聞き取りにくく、お客様に何度も聞き返させてしまうかもしれません。反対に、ゆっくりすぎると間延びした印象を与え、お客様をイライラさせてしまう可能性もあります。
相手のペースに合わせることを意識しつつ、落ち着いて、明瞭に話すことが求められます。声のトーンは、意識的に「ドレミファソ」の「ソ」の音をイメージすると、自然と明るく聞き取りやすい高さになると言われています。ぜひ試してみてください。
不適切な対応が招く機会損失とは
もし電話対応が不適切だったら、具体的にどのような損失につながるのでしょうか。最も直接的なのは、予約の取りこぼしです。例えば、電話口で待たされた挙句、「担当者がいないので分かりません」と曖昧な対応をされたら、お客様はどう思うでしょうか。「別のお店を探そう」と考えるのが自然ですよね。これは、本来得られるはずだった売上を逃す「機会損失」に他なりません。ある居酒屋での事例です。
週末の予約をしようと電話したお客様が、スタッフから「今、忙しいんで、後でかけ直してもらえますか」と一方的に言われてしまいました。お客様は不快に思い、結局別のお店に予約を入れました。そのお客様は会社の飲み会の幹事で、本来なら20名ほどの予約が見込めたかもしれません。たった一本の電話での不適切な対応が、大きな売上損失につながった典型的な例です。また、機会損失は売上だけにとどまりません。不快な思いをしたお客様は、その経験を友人や同僚に話したり、SNSや口コミサイトに書き込んだりする可能性があります。
そうなると、お店の評判が悪化し、新規顧客の獲得が難しくなるだけでなく、既存顧客の足も遠のいてしまうかもしれません。「あの店、料理は美味しいけど電話対応が最悪だから行きたくない」といったネガティブな評判は、想像以上に早く広まるものです。さらに、採用面にも影響が出ることがあります。お店の評判は、求職者もチェックしています。電話対応が悪いという評判が立てば、「スタッフを大切にしないお店なのかな」と思われ、人材確保が困難になる可能性も否定できません。このように、不適切な電話対応は、短期的な売上減だけでなく、長期的な評判低下や人材難といった、深刻な経営課題を引き起こすリスクをはらんでいるのです。
顧客満足度とリピート率への影響
丁寧で質の高い電話対応は、顧客満足度を向上させ、リピーター獲得に大きく貢献します。お客様は、予約や問い合わせの段階で気持ちの良い対応を受けると、「このお店なら安心して利用できそう」「大切に扱ってくれている」と感じ、来店前からお店に対する期待感や好感度が高まります。そして、実際に来店した際の体験と合わせて、総合的な満足度へとつながっていくのです。例えば、アレルギーを持つお子様連れの家族からの予約電話があったとします。
その際、スタッフがアレルギーの詳細を丁寧に聞き取り、「シェフと相談し、〇〇のメニューでしたら対応可能です。他に何かご心配な点はございますか」と親身に対応したとしましょう。この家族は、お店の配慮に感謝し、安心して食事を楽しむことができるでしょう。そして、「あのお店は子供のアレルギーにもしっかり対応してくれて、とても親切だった」と、良い印象を持ち、また利用したいと思う可能性が高まります。これがリピート率の向上に繋がるのです。逆に、電話対応で不安や不満を感じさせてしまうと、
たとえ料理が美味しくても、お客様の心にはネガティブな記憶が残り、再来店にはつながりにくくなります。「料理はまあまあだったけど、電話の人の感じが悪かったから、もう行かないかな」と思われてしまうのは非常にもったいないことです。顧客満足度は、単に来店時のサービスだけで決まるのではなく、来店前の電話対応から始まっているという意識を持つことが重要です。電話一本一本を、お客様との大切な関係性を築く第一歩と捉え、丁寧に対応することで、お店のファンを増やし、安定した経営の基盤となるリピーターを着実に育てていくことができるでしょう。
このように、電話対応はお店の印象を決定づける重要な要素であり、売上や評判、顧客満足度に直接的な影響を与えます。では、具体的にどのような準備をして電話対応に臨めば、お客様に好印象を与え、スムーズなコミュニケーションを実現できるのでしょうか。次に、そのための事前準備について詳しく見ていきましょう。
スムーズな対応を実現する事前準備とは
最新の予約状況と空席情報を把握する
お客様からの電話で最も多い問い合わせの一つが、予約に関するものです。「〇日の〇時に〇名で予約したいのですが、空いていますか」といった問い合わせに、即座に、かつ正確に答える必要があります。そのためには、常に最新の予約状況と空席情報を把握しておくことが不可欠です。多くの飲食店では、予約管理システムや予約台帳を使用していると思いますが、大切なのはその情報が常に最新であること、そして電話を取る可能性のあるスタッフ全員がその情報にアクセスし、内容を理解していることです。
例えば、あるスタッフが電話で予約を受けたのに、その情報をシステムや台帳にすぐに入力しなかったとします。その後、別のスタッフが同じ日時の問い合わせを受け、「空いていますよ」と答えてしまうと、ダブルブッキングが発生してしまいます。これは、お客様に多大な迷惑をかけるだけでなく、お店の信用を著しく損なう事態です。こうしたミスを防ぐためには、予約が入ったりキャンセルされたりしたら、即座に情報を更新するルールを徹底する必要があります。また、紙の台帳を使っている場合は、誰が見ても分かるように、丁寧な字で記入することも大切です。さらに、単に空席があるかどうかだけでなく、「カウンター席なら空いている」「〇時までならテーブル席が利用可能」といった、より詳細な情報まで把握しておくと、お客様への提案の幅が広がります。
「あいにくテーブル席は満席なのですが、カウンター席でしたら〇時からご用意できますがいかがでしょうか」といった代替案をスムーズに提示できれば、お客様の満足度も高まるでしょう。空席状況は常に変動するため、電話を受ける前やシフトの交代時には、必ず最新の情報を確認する習慣をつけることが重要です。これは、スムーズな予約受付の基本であり、トラブルを未然に防ぐための必須事項と言えます。
メニューやコース内容、アレルギー情報を整理しておく
予約や空席確認と並んで多いのが、メニューやコースに関する問い合わせです。「今日のオススメは何ですか」「〇〇コースの内容を教えてください」「子供向けのメニューはありますか」といった質問に、的確に答えられるように準備しておく必要があります。そのためには、まず自分自身がお店のメニュー(グランドメニュー、季節メニュー、ドリンクメニュー、コース内容など)をしっかりと把握しておくことが大前提です。特に、コース料理の場合は、品数、料理の内容、料金、利用可能な時間帯、予約の要不要などを正確に説明できなければなりません。
例えば、「接待で利用したいのですが、個室で利用できる〇〇円くらいのコースはありますか」という問い合わせがあったとしましょう。この時、コース内容や料金、個室利用の可否などをスムーズに説明できれば、お客様は安心して予約を検討できます。しかし、「少々お待ちください…えっと…」と確認に時間がかかったり、曖昧な説明しかできなかったりすると、お客様は不安を感じてしまうでしょう。さらに重要なのが、アレルギーや苦手食材に関する情報です。近年、食物アレルギーを持つお客様は増えています。
「〇〇アレルギーがあるのですが、対応可能ですか」「この料理に〇〇は使われていますか」といった問い合わせに、正確かつ迅速に答えられる体制を整えておくことは、お客様の安全を守る上で非常に重要です。メニューごとに使用されている食材、特にアレルゲンとなりやすい特定原材料(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生など)については、一覧表を作成するなどして、誰でもすぐに確認できるようにしておくと良いでしょう。ただし、アレルギーに関する情報は非常にデリケートであり、安易な回答は禁物です。不明な点や判断に迷う場合は、必ずキッチンスタッフや責任者に確認し、正確な情報をお客様に伝えるように徹底してください。
「たぶん大丈夫だと思います」といった曖昧な回答は絶対に避けましょう。これらの情報を事前に整理し、スタッフ間で共有しておくことで、お客様からの問い合わせに自信を持って、かつ安全に対応できるようになります。
よくある質問とその回答を準備する
日々の電話対応の中では、予約やメニュー以外にも、様々な質問が寄せられます。「駐車場はありますか」「最寄り駅からの行き方を教えてください」「個室はありますか」「子供連れでも大丈夫ですか」「ドレスコードはありますか」「クレジットカードは使えますか」など、頻繁に聞かれる質問については、あらかじめ回答をまとめておく(FAQを作成する)と非常に便利です。FAQを準備しておくことには、いくつかのメリットがあります。
第一に、誰が電話に出ても、迅速かつ正確に、そして統一された回答ができるようになります。これにより、スタッフによる対応のばらつきを防ぎ、お店全体の対応品質を高めることができます。新人スタッフでも、FAQを参照すれば安心して対応できるため、教育時間の短縮にも繋がるでしょう。第二に、お客様をお待たせする時間を短縮できます。よく聞かれる質問に対して、その都度確認していては時間がかかり、お客様をイライラさせてしまうかもしれません。FAQがあれば、即座に回答できるため、スムーズな対応が可能になります。
第三に、より複雑な問い合わせや個別対応が必要なケースに、時間と集中力を使うことができます。定型的な質問にFAQで効率的に対応できれば、その分、丁寧な対応が求められる場面で余裕を持って臨むことができるでしょう。例えば、あるカフェでは、Wi-Fiの有無、電源コンセントの利用可否、ペット同伴の可否、ベビーカーでの入店の可否などをまとめたFAQシートを電話機の近くに常備しています。これにより、アルバイトスタッフでもこれらの質問にスムーズに答えられるようになり、お客様からの評価も上がりました。FAQを作成する際は、過去の問い合わせ内容をリストアップし、それぞれの質問に対する分かりやすく簡潔な回答を用意します。そして、その内容を定期的に見直し、最新の情報に更新していくことが重要です。お店のウェブサイトにもFAQページを設けておけば、お客様が自己解決できるケースも増え、電話問い合わせの件数自体を減らす効果も期待できます。
これらの事前準備をしっかりと行うことで、電話対応における多くの問題を未然に防ぎ、お客様に安心感と信頼感を与えることができます。準備が整ったら、次はいよいよ実践です。特に重要な予約電話において、具体的にどのような点を確認し、どのように伝えれば良いのか、その極意を見ていきましょう。
予約電話で確認すべき必須項目と伝え方
日時、人数、氏名、連絡先を正確にヒアリングする
予約受付の基本中の基本は、「いつ」「何名で」「どなたが」「連絡先は」という4つの情報を正確に聞き取ることです。これらの情報に誤りがあると、お客様が来店された際に席が用意できていなかったり、予約内容の確認連絡が取れなかったりといった、深刻なトラブルにつながりかねません。まず「日時」については、「〇月〇日、〇曜日、〇時」というように、年月日、曜日、時間まで具体的に確認します。曜日まで確認することで、「〇日」の聞き間違いを防ぐ効果があります。時間は「午後7時」なのか「午前7時」なのか、あるいは「19時」なのかを明確にしましょう。
次に「人数」ですが、「大人〇名様、お子様〇名様」というように、大人と子供の内訳まで確認すると、席の準備や子供用椅子の用意などがスムーズになります。お子様の年齢も可能であれば聞いておくと、より細やかな対応が可能です。そして「氏名」は、漢字の確認まで行うのが理想的です。特に珍しいお名前や同姓のお客様が多い場合は、「失礼ですが、どのような漢字をお書きになりますか」と丁寧に伺いましょう。フルネームで伺うのが基本です。最後に「連絡先」ですが、携帯電話の番号など、日中確実に連絡が取れる番号を伺います。
万が一、予約内容の確認や変更が必要になった場合に備え、非常に重要です。これらの情報をヒアリングする際は、復唱確認を徹底することが極めて重要です。「〇月〇日、〇曜日、午後7時、大人2名様、お子様1名様、〇〇様、お電話番号は〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇でよろしいでしょうか」というように、お客様に確認していただくことで、聞き間違いや記入ミスを防ぐことができます。例えば、あるレストランで「7時」の予約を「指示」と聞き間違えてしまい、お客様が来店されたときに予約が入っていなかったというミスがありました。もし復唱確認をしていれば、このミスは防げたはずです。基本的な情報だからこそ、油断せずに一つ一つ丁寧に対応することが、信頼されるお店への道筋となるでしょう。
アレルギーや苦手食材、特別な要望の確認方法
基本的な予約情報(日時、人数、氏名、連絡先)の確認と合わせて、お客様の安全と満足度を高めるために、アレルギーや苦手食材の有無、その他の特別な要望についてもお伺いすることが推奨されます。特にアレルギー対応は、お客様の健康に関わる非常に重要な事項です。確認する際は、「アレルギーや苦手な食材はございますでしょうか」と直接的に、かつ丁寧な言葉遣いで伺いましょう。もし「ある」と答えられた場合は、具体的なアレルゲン(何に対してアレルギーがあるか)や、どの程度の配慮が必要か(微量でもダメなのか、加熱すれば大丈夫なのかなど)を詳しくヒアリングします。
ただし、電話口で即座に対応可否を判断できない場合や、詳細な確認が必要な場合は、「確認して折り返しご連絡いたします」と伝え、必ずキッチンスタッフや責任者に相談しましょう。安易な回答は絶対に避けるべきです。例えば、小麦アレルギーのお客様から予約があった際、「グルテンフリーのパスタに変更できますか」と聞かれたとします。その場で「できますよ」と答えるのではなく、「キッチンに確認いたしますので、少々お待ちいただけますでしょうか」または「確認後、改めてご連絡させていただいてもよろしいでしょうか」と対応するのが適切です。
苦手食材についても同様に確認し、可能な範囲で対応できるかどうかを伝えます。また、「お誕生日のお祝いで利用したいのですが」「静かな席をお願いできますか」「車椅子での利用は可能ですか」といった特別な要望についても、予約の段階で把握しておくことが大切です。これらの情報を事前に共有しておくことで、当日スムーズな対応が可能となり、お客様の期待に応えることができます。例えば、記念日利用のお客様にはデザートプレートを用意したり、車椅子のお客様には入り口に近い席やスペースに余裕のある席を確保したりといった配慮ができます。
これらの確認は、お客様への「おもてなし」の心を形にする重要なプロセスです。ただし、全ての要望に応えられるとは限りません。対応が難しい場合は、正直にその旨を伝え、代替案を提示するなど、誠実な対応を心がけることが重要です。「申し訳ございませんが、完全な個室はご用意がないのです。ただ、奥まった半個室風のお席でしたらご案内できますが、いかがなさいますか」といった具合です。
予約内容の復唱と最終確認の重要性
予約に必要な情報を一通りヒアリングし、特別な要望なども確認したら、必ず最後にもう一度、予約内容全体を復唱し、お客様に最終確認をしていただくことが極めて重要です。これは、聞き間違いや認識の齟齬を防ぎ、予約を確定させるための最後の砦となります。「それでは、ご予約内容を復唱させていただきます。〇月〇日、〇曜日、午後7時より、大人〇名様、お子様〇名様、〇〇様のお名前で承りました。お電話番号は〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇。また、〇〇のアレルギーがおありとのことですので、キッチンと連携して対応させていただきます。他に何かご不明な点や、追加のご要望はございますでしょうか」といった形で、ゆっくり、はっきりと復唱します。
この復唱には、いくつかのメリットがあります。まず、前述の通り、聞き間違いや記入漏れがないかをお客様と一緒に最終チェックできます。もし間違いがあれば、この段階で修正することが可能です。次に、お客様に安心感を与えることができます。予約内容が正確に伝わっていることを確認できれば、お客様は「ちゃんと予約が取れたな」と安心し、当日を楽しみに待つことができるでしょう。さらに、キャンセルポリシーや注意事項など、お店から伝えておくべき事項があれば、このタイミングで付け加えることができます。例えば、「キャンセルや人数変更の場合は、前日までにご連絡をお願いいたします」「当日はお時間通りにお越しいただけますようお願いいたします」といった一言を添えることで、無断キャンセルなどを抑制する効果も期待できます。
あるビストロでは、予約の最後に必ず「ご予約ありがとうございます。〇〇様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております」という一言を添えるようにしたところ、お客様からの「電話の感じが良かった」という声が増え、予約の無断キャンセルも減少したそうです。復唱と最終確認は、単なる事務的な作業ではなく、お客様との信頼関係を築き、気持ちよく来店していただくための重要なコミュニケーションなのです。このひと手間を惜しまないことが、結果的にトラブルを防ぎ、お店の評価を高めることに繋がります。
予約電話で正確な情報を聞き取り、丁寧な確認を行うことで、お客様は安心して来店日を迎えることができます。さて、電話対応は予約だけではありません。お店の場所や営業時間、メニューの詳細など、様々な問い合わせの電話もかかってきます。次に、これらの問い合わせに的確かつ丁寧に対応するためのコツについて見ていきましょう。
問い合わせに的確かつ丁寧に対応するコツ
質問の意図を正確に理解する傾聴スキル
お客様からの問い合わせに対応する際、まず最も大切なのは、相手が「何を知りたいのか」「何を求めているのか」を正確に理解することです。そのためには、相手の話を注意深く聞く「傾聴スキル」が欠かせません。ただ単に言葉を聞き取るだけでなく、声のトーンや話し方から、お客様の状況や感情を読み取ることも意識しましょう。例えば、「個室はありますか」という質問。
この質問の裏には、「子供連れなので周りに気兼ねなく過ごしたい」「接待で使いたいので静かな空間が必要」「サプライズをしたいので他の客から見えない場所がいい」など、様々な背景や意図が隠れている可能性があります。単に「はい、ございます」または「いいえ、ございません」と答えるだけでなく、「どのようなご利用シーンでしょうか」と一歩踏み込んで質問することで、お客様の真のニーズを把握し、より的確な情報提供や提案に繋げることができます。また、お客様が話している途中で遮ったり、自分の思い込みで判断したりせず、最後までしっかりと話を聞く姿勢が重要です。「なるほど」「さようでございますか」といった相槌を適度に打ち、相手が話しやすい雰囲気を作ることも効果的です。
もし質問の内容が曖昧だったり、理解しにくい場合は、「恐れ入ります、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか」や「〇〇ということでしょうか」と、遠慮せずに確認しましょう。分かったふりをして不正確な情報を提供してしまう方が、よほど失礼にあたります。例えば、「駐車場について聞きたいんだけど」という漠然とした問い合わせの場合、「はい、駐車場についてですね。ご利用可能な台数でしょうか、それとも場所についてでしょうか」というように、具体的な質問内容をこちらから確認することで、スムーズなやり取りが可能になります。傾聴スキルは、単に情報を得るためだけでなく、お客様に「ちゃんと話を聞いてくれている」「真剣に対応してくれている」という安心感を与えるための重要なスキルなのです。
不明瞭な点を確認し、正確な情報を提供する
お客様の質問の意図を理解したら、次はその質問に対して正確な情報を提供することが求められます。ここで重要なのは、「正確さ」と「分かりやすさ」です。どんなに丁寧な言葉遣いをしても、提供する情報が間違っていたり、曖昧だったりしては意味がありません。特に、営業時間、料金、メニュー内容、アクセス方法など、お客様の判断や行動に直接関わる情報については、絶対に間違いのないように注意が必要です。もし、質問された内容について正確な情報が分からない場合や、自信がない場合は、正直にその旨を伝え、確認してから回答するようにしましょう。
「申し訳ございません、ただ今確認いたしますので、少々お待ちいただけますでしょうか」と伝え、保留にするか、確認後に折り返し連絡するなどの対応をとります。その際、保留が長くなりそうな場合は、途中で「お待たせして申し訳ございません。もう少々お時間がかかりそうです」と中間報告を入れる気配りが大切です。「たぶん〇〇だと思います」「おそらく大丈夫でしょう」といった憶測や曖昧な表現は、誤解やトラブルの原因となるため絶対に避けなければなりません。例えば、「〇〇駅から歩いて何分くらいですか」という質問に対して、正確な時間が分からなければ、「申し訳ございません、正確な所要時間は分かりかねますが、一般的には徒歩で〇分から〇分程度のお客様が多いようです。
地図アプリなどでご確認いただくのが確実かと存じます」といったように、分かる範囲の情報と、より確実な確認方法を伝えるのが良いでしょう。また、情報を伝える際には、専門用語や業界用語を避け、誰にでも分かりやすい言葉で説明することを心がけます。例えば、コース料理の説明をする際に、料理専門の用語を多用するのではなく、「〇〇産の新鮮な魚介を使ったカルパッチョでございます」といった具体的な表現を用いる方が、お客様には伝わりやすくなります。正確な情報を、分かりやすく、そして自信を持って伝えることが、お客様の信頼を得るための鍵となります。
代替案の提示や解決に向けた姿勢を示す
問い合わせの中には、お客様の要望に完全には応えられないケースもあります。例えば、「今日、予約なしで〇時に行きたいんだけど、入れますか」という問い合わせに対し、満席で案内できない場合。「〇〇アレルギーがあるんだけど、このコースは食べられますか」という質問に対し、対応が難しい場合などです。このような場合、単に「できません」「無理です」と断るだけでは、お客様はがっかりし、お店に対してネガティブな印象を持ってしまうでしょう。たとえ要望に応えられなくても、お客様の気持ちに寄り添い、できる限りの代替案を提示したり、解決に向けて努力する姿勢を見せたりすることが非常に重要です。
例えば、満席で案内できない場合でも、「申し訳ございません、あいにくそのお時間は満席でございます。もしよろしければ、〇時以降でしたらお席が空く可能性がございますが、いかがでしょうか」や、「本日は難しいのですが、明日の同じ時間でしたらまだ空きがございます」といった代替案を提示することで、お客様は「自分のために考えてくれている」と感じ、次回の利用に繋がる可能性があります。アレルギー対応が難しい場合でも、「申し訳ございません、コース料理での完全な対応は難しいのですが、アラカルトメニューの中からでしたら、〇〇様にお召し上がりいただけるお料理もいくつかございます。もしよろしければ、いくつかご紹介いたしましょうか」といった提案ができれば、お客様の選択肢を示すことができます。
重要なのは、「できない」という事実だけでなく、「何かできることはないか」という前向きな姿勢を示すことです。例えば、あるお客様が希望した銘柄のワインが品切れだった場合。「申し訳ございません、そちらは現在品切れでして…」で終わるのではなく、「大変申し訳ございません。そちらのワインはあいにく品切れなのですが、同じようなタイプの〇〇でしたらご用意がございます。お客様がお好みでした〇〇と非常に似た味わいで、こちらも大変おすすめなのですが、いかがでしょうか」と代替案をスムーズに提案できれば、お客様の満足度を損なわずに済むかもしれません。このように、お客様の要望に応えられない状況でも、親身になって代替案を探す姿勢を見せることが、結果的に顧客満足度を高め、お店への信頼を深めることに繋がるのです。
傾聴、正確な情報提供、そして代替案の提示。これらのコツを押さえて丁寧に対応すれば、多くのお客様は満足し、お店への好印象を持ってくれるはずです。しかし、どんなに気をつけていても、時にはお客様の期待に応えられなかったり、誤解が生じたりして、クレームに繋がってしまう可能性もゼロではありません。次に、クレームにつながりやすい要注意ポイントと、それを未然に防ぐための回避策について解説します。
クレームにつながりやすい要注意ポイントと回避策
満席時や対応不可の場合の丁寧な断り方
お客様からの予約希望や要望に対して、「満席です」「できません」と、ただストレートに断ってしまうのは、たとえ事実であっても、お客様にとっては非常に冷たく、突き放されたような印象を与えかねません。これがクレームの引き金になることは少なくありません。特に、楽しみにしていたお店に断られたり、特別な要望をあっさり拒否されたりすれば、お客様が不満を感じるのは当然のことです。重要なのは、「断る」というネガティブな情報を伝える際に、いかに相手の気持ちに配慮し、丁寧な言葉遣いとクッション言葉を用いるか、そして可能であれば代替案を提示するか、という点です。
NG例としては、「あー、その時間、満席なんで無理です」「うちはそういうのやってないんで」といった、ぶっきらぼうな言い方が挙げられます。これでは、お客様は「客として扱われていない」と感じてしまうでしょう。回避策としては、まず「申し訳ございません」「あいにくですが」といったクッション言葉を使って、お断りすることへの謝意や残念な気持ちを示します。その上で、「〇時のお席はあいにく満席でございます」のように、丁寧な言葉で事実を伝えます。さらに、「もしよろしければ、〇時からでしたらお席をご用意できますが、いかがでしょうか」や「大変申し訳ございませんが、当店では〇〇のご要望にはお応えしかねる状況でございます。
ただ、〇〇でしたら可能ですが…」のように、代替案を提示することで、お客様の落胆を和らげ、前向きな印象を与えることができます。たとえ代替案が受け入れられなかったとしても、「お客様のために何とかしよう」という姿勢を示すことが大切です。例えば、ある人気店では、満席でお断りする際に、「大変申し訳ございません。本日は終日満席を頂戴しております。せっかくお電話いただいたのに、本当に申し訳ございません。もしよろしければ、キャンセルが出た際にご連絡させていただくことも可能ですが、いかがなさいますか」といった対応を徹底しています。このように、断る際にも最大限の配慮を示すことで、お客様の不満を最小限に抑え、むしろ丁寧な対応に好印象を持ってくれる可能性すらあるのです。
保留が長引く場合の適切な中間報告
問い合わせの内容を確認したり、担当者に取り次いだりするために、お客様に電話口で待っていただく「保留」は、やむを得ない場面も多いでしょう。しかし、この保留時間が長引くと、お客様は「忘れられているのではないか」「いつまで待たされるのだろう」と不安やイライラを感じ始め、クレームの原因となることがあります。特に、何の断りもなく長時間保留にしたり、保留が解除されたと思ったらまたすぐに保留にしたり、といった対応は、お客様の不快感を増幅させます。
保留にする際は、まず「確認いたしますので、少々お待ちいただけますでしょうか」と、必ずお客様の許可を得てから行います。そして、保留時間の目安を伝えることも有効です。「1分ほどお待ちいただけますでしょうか」のように具体的な時間を伝えられれば、お客様も安心して待つことができます。もし、確認に予想以上に時間がかかり、目安の時間を超えてしまいそうな場合は、一度保留を解除し、「大変お待たせして申し訳ございません。もう少々お時間がかかりそうです。このままお待ちいただけますでしょうか、それとも後ほどこちらからおかけ直しいたしましょうか」と、中間報告とお伺いを立てることが非常に重要です。
これにより、お客様は自分が放置されていないことを認識でき、待つことへのストレスが軽減されます。NG例としては、無言で保留ボタンを押したり、3分以上も何の連絡もなく待たせたりすることが挙げられます。ある調査では、電話の保留時間は1分を超えると多くの人がストレスを感じ始めると言われています。これを避けるためには、30秒~1分程度を目安に、一度状況を報告するのが望ましいでしょう。例えば、担当者が他の電話に出ているためにすぐ取り次げない場合。「〇〇(担当者名)はただ今他の電話に出ておりまして、終わり次第代わらせますので、恐れ入りますがもう少々お待ちいただけますでしょうか」と具体的に理由を伝えることで、お客様の理解を得やすくなります。保留は、お客様の貴重な時間をいただいているという意識を持ち、できるだけ短く済ませる努力と、長引く場合の丁寧な中間報告を徹底することが、クレーム回避の鍵となります。
曖昧な回答や安請け合いを避ける
お客様からの質問や要望に対し、よく分からないまま「たぶん大丈夫だと思います」「おそらくできるでしょう」といった曖昧な回答をしてしまったり、その場の雰囲気に流されて安易に「はい、できます」「お任せください」と安請け合いしてしまったりすることも、後々大きなクレームに繋がる危険なポイントです。なぜなら、お客様はその言葉を信じて期待してしまうからです。もし、その期待に応えられなかった場合、「電話ではできると言ったじゃないか」「約束が違う」という強い不満や怒りを招くことになります。
特に、アレルギー対応、個室の確約、特定の食材の用意など、お客様にとって重要な事項に関する曖昧な回答や安請け合いは、絶対に避けなければなりません。NG例としては、「〇〇アレルギー? ああ、たぶん大丈夫ですよ」と根拠なく答えてしまうことや、「個室、取っておきますよ」と確約できないのに言ってしまうことなどが挙げられます。回避策としては、まず、分からないこと、確信が持てないことについては、決して憶測で答えない、という原則を徹底することです。「確認いたします」「担当者に確認して折り返しご連絡いたします」など、正確な情報を確認するための時間をもらうようにしましょう。また、要望に対して「できるかどうか」が不確実な場合は、安易に「できる」と断言せず、「〇〇については、できる限りご要望に沿えるよう努力いたしますが、確約はできかねます。申し訳ございません」といったように、正直に伝えることが重要です。
もちろん、できる限りお客様の要望に応えようと努力する姿勢は大切ですが、できない可能性があるのであれば、それを正直に伝える方が、結果的にクレームを防ぐことに繋がります。例えば、「窓際の景色の良い席をお願いしたい」という要望があった場合。「はい、承知いたしました」と安請け合いするのではなく、「窓際のお席ですね。承知いたしました。当日の状況にもよりますが、できる限りご希望に沿えるよう調整いたします」といった伝え方であれば、お客様も過度な期待をせず、お店側もプレッシャーを感じすぎずに済みます。誠実であること、正直であることが、お客様との信頼関係を築き、無用なクレームを避けるための基本姿勢と言えるでしょう。
これらのクレームにつながりやすいポイントを理解し、適切な対応を心がけることで、電話対応におけるトラブルは大幅に減らせるはずです。常に相手の立場に立ち、丁寧で誠実なコミュニケーションを意識することが大切です。それでは最後に、これまでの内容をまとめて、質の高い電話対応がお店にもたらす価値について再確認しましょう。
まとめ
今回は、飲食店スタッフなら必ず押さえておきたい電話対応の基本から、予約・問い合わせ対応の具体的なコツ、そしてクレームを未然に防ぐためのポイントまで、幅広く解説してきました。電話対応は、お客様がお店と最初に接する重要な窓口であり、その印象がお店全体の評価、ひいては売上やリピート率にまで影響を与えることをご理解いただけたかと思います。明るく聞き取りやすい声と丁寧な言葉遣いはもちろんのこと、お客様の状況や要望を正確に把握するための傾聴力、必要な情報を分かりやすく伝えるための準備と説明力、そして時には要望に応えられない場合でも誠意をもって対応する姿勢が求められます。
特に、予約対応では日時・人数・氏名・連絡先の正確なヒアリングと復唱確認、アレルギーや特別な要望への配慮が不可欠です。問い合わせ対応では、質問の意図を汲み取り、正確な情報を提供し、必要であれば代替案を示すことが顧客満足度を高めます。そして、満席時の断り方、保留の扱い、曖昧な回答の回避といったクレームにつながりやすいポイントを意識することで、トラブルを未然に防ぐことができます。これらのスキルは、一朝一夕に身につくものではありませんが、日々の業務の中で意識し、実践し続けることで、必ず向上していきます。
質の高い電話対応は、単なる作業ではなく、お客様をおもてなしする心そのものです。心のこもった丁寧な対応は、お客様に安心感と信頼感を与え、「またこのお店に来たい」と思わせる力を持っています。ぜひ、この記事で紹介したポイントを参考に、あなたのお店の電話対応をさらにレベルアップさせ、お客様から愛され、選ばれ続けるお店を目指してください。質の高い電話対応を通じて、お店のファンを一人でも多く増やしていくことが、これからの飲食店経営においてますます重要になっていくでしょう。

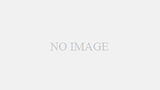
コメント