医療機関の顔とも言える受付や、患者さんと直接関わる看護師の電話対応は、クリニックや病院の印象を大きく左右する重要な要素です。不安を抱えて電話をかけてくる患者さんにとって、電話口での丁寧で適切な対応は、安心感と信頼感につながります。逆に、少しの言葉遣いのミスや配慮の欠けた対応が、不信感を招き、時にはクレームに発展することも少なくありません。
この記事では、医療機関で働く受付スタッフや看護師の方々が、患者さんから「この病院なら安心できる」と思っていただけるような、電話対応の基本的なマナーから、具体的なシーン別の対応術、そしてスキルアップのためのトレーニング方法まで、詳しく解説していきます。日々の電話対応を見直し、より質の高い医療サービス提供の一助となれば幸いです。患者さんとの良好な関係構築は、電話対応という最初の接点から始まります。
医療機関における電話対応の重要性:信頼の第一歩
患者満足度への直接的な影響
電話対応の質は、患者満足度に直接的な影響を与えます。考えてみてください。体調が悪く、不安な気持ちで病院に電話をした際、冷たい対応や事務的な口調で応じられたら、どのように感じるでしょうか。おそらく、不安が増し、不快な気持ちになるはずです。逆に、電話口のスタッフが親身になって話を聞き、丁寧な言葉遣いで分かりやすく説明してくれたら、それだけで心が少し軽くなり、「この病院なら安心して診てもらえそうだ」と感じるのではないでしょうか。
たとえば、ある患者さんが高熱で苦しんでいる時に電話をしたとします。受付担当者が「はい、〇〇クリニックです。どうされましたか」と落ち着いた優しい声で応じ、「熱が高いのですね、お辛いでしょう。すぐに診察できるよう手配しますので、〇時頃いらしてください」と具体的な案内をしてくれたら、患者さんは非常に安心するでしょう。このように、電話対応一つで患者さんの心理的な負担は大きく軽減され、医療機関に対する満足度や信頼度は格段に向上します。これは、予約の電話だけでなく、問い合わせや検査結果の確認など、あらゆる電話でのやり取りに共通して言えることです。
患者さんは、医療技術だけでなく、スタッフの対応を含めた総合的な体験で医療機関を評価します。ゆえに、電話対応は患者満足度を高めるための重要な要素なのです。補足すると、患者満足度の向上は、口コミによる評判の向上にも繋がり、結果として新規患者の獲得にも貢献します。
クリニックの評判とイメージ形成
電話対応は、クリニックや病院の評判とイメージ形成においても、極めて重要な役割を担っています。電話は、多くの患者さんにとって医療機関との最初の接点です。この最初のコンタクトで受けた印象が、その医療機関全体のイメージとして定着しやすい傾向があります。たとえば、電話をかけた際に何度も待たされたり、担当者間でたらい回しにされたり、あるいは質問に対して曖昧な回答しか得られなかったりした場合、患者さんは「ここは連携が取れていない」「スタッフの教育が不十分だ」といったネガティブな印象を抱く可能性が高いです。
このような経験は、たとえ診察自体は丁寧であったとしても、クリニック全体の評価を下げる要因となり得ます。現代では、インターネット上の口コミサイトやSNSを通じて、個人の体験が瞬時に共有される時代です。電話対応に関する否定的な書き込みは、多くの人の目に触れ、クリニックの評判に悪影響を及ぼしかねません。逆に、常に丁寧で迅速、かつ的確な電話対応を心がけている医療機関は、「スタッフの対応が良い」「安心して相談できる」といった好意的な評判が広がりやすくなります。
例えば、「〇〇クリニックの受付の方は、いつも電話で丁寧に症状を聞いてくれて、適切な科を案内してくれるから助かる」といった口コミは、潜在的な患者にとって大きな安心材料となり、来院のきっかけにもなり得ます。すなわち、日々の電話対応の積み重ねが、地域社会におけるクリニックの良好な評判と、信頼されるイメージを形作っていくのです。
スムーズな診療連携への貢献
質の高い電話対応は、院内および院外とのスムーズな診療連携にも大きく貢献します。医療現場では、医師、看護師、検査技師、事務スタッフなど、多くの職種が連携して患者さんの治療にあたっています。電話は、これらのスタッフ間での情報伝達や、他の医療機関、検査センター、薬局などとの連携においても頻繁に使用されるツールです。電話対応において、情報を正確に聞き取り、簡潔かつ明確に伝えるスキルは、診療プロセス全体の効率化と安全性向上に不可欠です。
たとえば、他の病院から紹介された患者さんの情報を受け取る際、電話で聞き取った内容に誤りがあれば、適切な診療計画の立案に支障をきたす恐れがあります。また、検査予約の電話で、患者さんの情報や必要な検査項目を正確に伝えられなければ、検査当日に混乱が生じたり、最悪の場合、検査が実施できないといった事態も起こり得ます。逆に、電話対応がスムーズであれば、必要な情報が迅速かつ正確に関係各所に伝わり、診療の遅延やミスを防ぐことができます。
救急患者の受け入れ要請があった際、電話で患者の状態、到着予定時刻、必要な処置などの情報を的確に聞き取り、院内の関係部署へ迅速に伝達できれば、受け入れ準備を万全に整え、スムーズな治療開始に繋げることが可能です。このように、適切な電話対応スキルは、院内連携を円滑にし、チーム医療の質を高める上で欠かせない要素なのです。さらに、薬局からの問い合わせに対して、処方内容を正確に伝えることも、患者さんの安全な薬物治療を支える上で重要です。次では、こうした質の高い電話対応を実現するための基本的なマナーについて掘り下げていきましょう。
【基本編】押さえておくべき電話マナーの基礎
明瞭な発声と適切な言葉遣い
電話対応において、明瞭な発声と適切な言葉遣いは、相手に正確な情報を伝え、かつ好印象を与えるための基本中の基本です。まず、発声に関しては、口をしっかりと開け、一語一語をはっきりと話すことを意識しましょう。特に、医療機関名や担当者名、数字や時間などは、聞き間違いが起こりやすいポイントです。早口になったり、語尾が不明瞭になったりしないよう、落ち着いて話すことが重要です。
たとえば、「〇〇クリニックです」と名乗る際も、ぼそぼそと話すのではなく、相手にクリアに聞こえるように発声します。また、電話は対面よりも音声が聞き取りにくい場合があるため、普段よりも少し大きめの声を意識すると良いでしょう。ただし、大きすぎると威圧的に聞こえる可能性もあるため、適度な音量を心がけてください。次に、言葉遣いです。医療機関のスタッフとして、丁寧語・謙譲語・尊敬語を正しく使い分けることが求められます。患者さんに対しては、常に尊敬語と丁寧語を基本とし、親しみを込める場合でも、馴れ馴れしい言葉遣いは避けるべきです。
患者さんからの問い合わせに対しては、「分かりました」ではなく「承知いたしました」や「かしこまりました」を使う、「〜してください」ではなく「〜していただけますでしょうか」や「〜をお願いいたします」といった依頼形を用いるなど、細やかな配慮が必要です。また、専門用語や略語は、患者さんには理解できない場合が多いため、できるだけ避け、平易な言葉で説明することを心がけましょう。たとえば、「バイタルサインを確認します」ではなく「体温や血圧などを測りますね」のように言い換える配慮が大切です。こうした適切な言葉遣いは、医療機関としてのプロフェッショナリズムを示すとともに、患者さんに敬意を払い、安心感を与える上で不可欠な要素となります。
聞き取りやすい声のトーンとスピード
声のトーンと話すスピードも、電話対応の印象を大きく左右する重要な要素です。顔が見えない電話では、声の調子が感情や態度を伝える唯一の手がかりとなります。まず、声のトーンですが、一般的に「ドレミファソラシド」の「ソ」の音階が、相手にとって最も聞き取りやすく、かつ明るく落ち着いた印象を与えると言われています。低すぎるトーンは不機嫌に聞こえたり、暗い印象を与えたりする可能性があります。逆に、高すぎるトーンは、場合によっては軽薄に聞こえたり、切迫感を与えたりすることもあります。したがって、意識的に「ソ」の音をイメージし、穏やかで安定したトーンを保つよう心がけましょう。
特に、患者さんが不安や痛みを訴えている場合には、より共感的で落ち着いたトーンで対応することが求められます。たとえば、予約変更の電話を受けた際、明るくハキハキとしたトーンで「はい、〇〇クリニックでございます」と応対し、変更理由を尋ねる際には少し落ち着いたトーンで「そうでございますか、お変わりございませんか」と気遣う言葉を添えるなど、状況に応じたトーンの使い分けが大切です。次に、話すスピードです。早口は、相手に情報を正確に伝えることを妨げるだけでなく、せかされているような印象や、落ち着きのない印象を与えてしまいます。特に、高齢の患者さんや、耳が聞こえにくい方に対しては、普段よりもゆっくりと、区切りながら話す配慮が必要です。一方で、あまりにもゆっくりすぎると、間延びした印象を与えたり、相手をイライラさせてしまう可能性もあります。
目安としては、相手の話すスピードに合わせるか、ややゆっくりめに話すことを意識すると良いでしょう。重要な情報を伝える際や、複雑な説明をする際には、特にスピードを落とし、相手が理解しているかを確認しながら進めることが重要です。たとえば、検査前の注意事項を説明する際には、「検査当日は、朝食を召し上がらずに、午前〇時までにご来院ください」のように、一つ一つの情報を区切りながら、少しゆっくりめに伝えることで、聞き間違いを防ぎ、患者さんの理解を深めることができます。
丁寧な傾聴と正確なメモ取り
電話対応において、相手の話を丁寧に聞き、その内容を正確に記録することは、コミュニケーションの基本であり、ミスの防止に不可欠です。まず、傾聴についてですが、これは単に相手の話を聞くだけでなく、相手の状況や感情に寄り添い、共感しながら聞く姿勢を指します。相槌を適切に打つ(「はい」「ええ」「さようでございますか」など)、相手の話を遮らずに最後まで聞く、話の内容を要約して確認する(「つまり、〇〇ということですね」)といった行動が、丁寧な傾聴の表れです。
これにより、患者さんは「自分の話をきちんと聞いてもらえている」と感じ、安心感を覚えます。たとえば、症状について説明している患者さんに対して、途中で話を遮って質問を始めたり、他の作業をしながら聞いているような態度をとったりするのは避けるべきです。相手の話に集中し、理解しようと努める姿勢を示すことが重要です。次に、正確なメモ取りです。電話でのやり取りは、後で確認することが難しいため、重要な情報は必ずメモを取る習慣をつけましょう。
特に、患者さんの氏名、連絡先、症状、問い合わせ内容、予約日時、担当者名などは、聞き間違いや記憶違いが起こりやすい項目です。5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して、情報を整理しながらメモを取ると、漏れや誤りを防ぐことができます。たとえば、予約の電話を受けた際には、患者さんのフルネーム(漢字も確認)、生年月日、電話番号、希望日時、簡単な症状などを聞き取り、復唱して確認しながらメモ帳やシステムに入力します。
聞き取れなかった場合や不明瞭な点があった場合は、遠慮せずに「恐れ入りますが、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか」と聞き返す勇気も必要です。曖昧なまま対応を進めると、後で大きなトラブルに繋がる可能性があります。ちなみに、メモを取る際には、専用のメモ帳やフォーマットを用意しておくと、記録の標準化や後での参照が容易になります。これらの基本的なマナーを身につけた上で、次は具体的なシーンに応じた対応術を見ていきましょう。
シーン別・患者さんが安心する電話対応術
予約受付・変更時のスムーズな案内
予約受付や変更の電話は、医療機関にとって最も頻繁にかかってくる電話の一つであり、スムーズかつ丁寧な対応が求められる場面です。まず、電話を受けたら、明るくはっきりとした声で医療機関名を名乗り、用件を伺います。「はい、〇〇クリニック、受付の△△が承ります。本日はどのようなご用件でしょうか」といった形で、丁寧に対応を始めましょう。予約希望の旨を聞いたら、まず患者さんの氏名(フルネーム)、生年月日、診察券番号(もしあれば)、連絡先を確認します。新規の患者さんの場合は、その旨を確認し、必要な情報を丁寧に聞き取ります。
次に、希望の診療科、医師、日時を伺います。希望日時が空いていない場合は、ただ「空いていません」と伝えるのではなく、「申し訳ございません、その日時はあいにく予約でいっぱいでございます。〇日の△時、または□日の×時はいかがでしょうか」のように、具体的な代替案をいくつか提示することが重要です。これにより、患者さんは選択肢の中から都合の良い日時を選びやすくなります。たとえば、内科の予約を希望された際に希望日時が埋まっていても、「〇〇先生でしたら、明日の午後3時と、明後日の午前10時に空きがございますが、いかがなさいますか」と提案することで、患者さんの手間を省き、親切な印象を与えることができます。
予約が確定したら、必ず予約日時、診療科、担当医師名、持ち物(保険証、診察券、お薬手帳など)、注意事項(食事制限など)を復唱し、患者さんに確認してもらいます。「それでは、ご予約内容を確認させていただきます。〇月〇日、△曜日、午前□時、内科の〇〇先生のご予約でございますね。当日は保険証と診察券をお持ちください。お間違いございませんでしょうか」のように、一つ一つ丁寧に確認することで、当日のトラブルを防ぎます。予約変更の場合も同様に、まず元の予約内容を確認し、その後、新しい希望日時を伺い、調整を行います。変更理由を尋ねる際には、「差し支えなければ、変更の理由をお伺いしてもよろしいでしょうか」と、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。患者さんの都合を尊重しつつ、スムーズに手続きを進めることが、信頼関係の構築に繋がります。
問い合わせに対する的確で分かりやすい回答
患者さんからは、診療時間、休診日、アクセス方法、特定の症状に関する相談、検査内容、費用など、様々な問い合わせの電話がかかってきます。これらの問い合わせに対して、的確かつ分かりやすく回答することは、患者さんの疑問や不安を解消し、医療機関への信頼を高める上で非常に重要です。まず、問い合わせ内容を正確に聞き取ることが第一歩です。相手が何を知りたいのか、どのような点に困っているのかを丁寧にヒアリングします。
もし、問い合わせ内容が複雑であったり、複数の質問が含まれていたりする場合は、メモを取りながら整理し、一つずつ確認していくと良いでしょう。回答する際には、専門用語を避け、できるだけ平易な言葉で説明することを心がけます。たとえば、「MRI検査について教えてほしい」という問い合わせがあった場合、「磁気共鳴画像診断装置という機械を使って、体の断面を詳しく見る検査です。強い磁石と電波を使いますが、放射線は使用しないので被ばくの心配はありません。検査時間は部位によって異なりますが、大体30分から1時間程度です」のように、具体的な内容を分かりやすく説明します。
また、電話口で即答できない質問や、医師の判断が必要な医学的な相談については、安易に回答せず、正直にその旨を伝えることが重要です。「申し訳ございません、その件につきましては、私では分かりかねますので、担当の者(または医師)に確認して、折り返しご連絡させていただいてもよろしいでしょうか」といった形で対応し、必ず担当者名と折り返しに必要な時間を伝え、迅速に対応します。曖昧な回答や不確かな情報は、かえって患者さんの混乱や不信感を招く原因となります。たとえば、症状に関する相談を受けた際に、「おそらく〇〇だと思います」といった自己判断での回答は絶対に避け、「症状について詳しくお伺いした上で、医師が診察させていただく必要がございます。
一度ご来院いただけますでしょうか」のように、適切な受診を促す対応が求められます。問い合わせ内容によっては、関連部署への取り次ぎが必要な場合もあります。その際は、保留にする前に必ず患者さんの了承を得て、保留が長くなる場合は、一度電話に戻り状況を説明するなど、丁寧な対応を心がけましょう。
緊急時の冷静かつ迅速な対応フロー
医療機関には、突然の事故や急病など、緊急性の高い電話がかかってくることもあります。このような状況では、電話を受けるスタッフの冷静かつ迅速な対応が、患者さんの生命や健康を守る上で極めて重要になります。まず、緊急の電話であると判断したら、何よりも落ち着いて対応することが大切です。パニックにならず、相手の話を注意深く聞き、状況を正確に把握することに努めます。電話口の相手も動揺している可能性が高いため、こちらが冷静さを保つことで、相手を落ち着かせる効果も期待できます。次に、必要な情報を効率的に聞き取る必要があります。緊急時に確認すべき主な項目としては、以下のものが挙げられます。
- 患者さんの氏名、年齢、性別
- 現在の状況(意識はあるか、呼吸はしているか、出血の有無、具体的な症状など)
- 発生場所(住所や目印など)
- 電話をかけている人の氏名と連絡先
- かかりつけ医や既往歴(もし分かれば)
これらの情報を、簡潔な質問で聞き出します。たとえば、「お名前とご年齢を教えていただけますか」「今、どのようなご様子ですか。意識はありますか」「どこで具合が悪くなられましたか」といった形で、落ち着いて質問を重ねます。情報を聞き取ると同時に、他のスタッフに応援を求めたり、医師や看護師へ状況を報告したりするなど、院内での連携を迅速に行う必要があります。緊急度が高いと判断される場合は、電話を繋いだまま、救急車の要請を指示したり、来院時の受け入れ準備(ベッドの確保、医療スタッフの手配など)を進めたりします。
たとえば、胸の痛みを訴える電話で、心筋梗塞などが疑われる場合は、すぐに医師に報告し、指示を仰ぎながら、患者さんや家族に救急車を呼ぶように伝える、あるいはクリニック側で手配するなどの対応が必要です。電話を切る前には、必ず相手の連絡先を再確認し、「救急車が到着するまで、またはこちらに向かう間、何か変化があれば再度ご連絡ください」と伝え、必要であれば応急処置の方法などを口頭で指示することもあります。
緊急時の対応は、事前のシミュレーションやマニュアルの整備が非常に重要です。定期的な研修を通じて、いざという時に慌てず、的確に行動できるよう備えておくことが求められます。このように、状況に応じた適切な対応を身につけることで、患者さんの安心と安全を守ることができます。しかし、一方で避けるべきNG対応も存在します。次では、信頼を損なう可能性のある電話対応について見ていきましょう。
要注意:信頼を損なう可能性のあるNG電話対応
専門用語の多用や説明不足
医療現場で日常的に使われている専門用語や略語は、患者さんにとっては理解が難しい場合がほとんどです。電話対応において、これらの専門用語を多用したり、説明が不十分だったりすると、患者さんは内容を正確に理解できず、不安や不信感を抱く原因となります。たとえば、検査予約の電話で「次回はエコー検査を行いますので、NPOでお願いします」とだけ伝えたとします。医療従事者にとっては「超音波検査で、絶食で来てください」という意味だとすぐに分かりますが、患者さんにとっては「エコー?」「NPOって何?」と疑問符が浮かぶばかりでしょう。
このような場合、「次回は超音波を使ってお腹の中を見る検査(エコー検査)を行います。検査当日は、朝食をとらずに、お水やお茶なども飲まずにお越しください」のように、専門用語を避け、具体的な行動を分かりやすい言葉で説明する必要があります。また、症状に関する問い合わせに対して、「おそらく〇〇炎の疑いがありますね。CRPの値を見てみないと何とも言えませんが」といった説明もNGです。患者さんは「〇〇炎」や「CRP」が何を指すのか分からず、ただ不安を煽られるだけになってしまいます。この場合は、「症状からすると〇〇という炎症の可能性も考えられますが、詳しいことは血液検査などを行わないと分かりません。一度診察を受けていただくのがよろしいかと思います」のように、憶測を避け、受診を促す方が適切です。
説明不足も同様に問題です。たとえば、予約変更の際に「その時間は予約が入っています」とだけ伝えるのではなく、「申し訳ございません、その時間帯はすでに他の患者様のご予約が入っております。他の時間帯では、〇時や△時はいかがでしょうか」と、理由と代替案を丁寧に伝えるべきです。患者さんは、なぜ自分の希望が通らないのか、他にどのような選択肢があるのかを知りたいと思っています。
説明が足りないと、「冷たい対応だ」「融通が利かない」といった不満につながりかねません。常に患者さんの視点に立ち、「この説明で相手は理解できるだろうか」「もっと分かりやすい言葉はないだろうか」と自問自答する姿勢が重要です。ちなみに、難しい内容を説明する際には、一度説明した後に「何かご不明な点はございますか」と問いかけ、質問の機会を設けることも有効です。
保留や折り返しの長時間化
電話対応において、保留や折り返し連絡が必要になる場面は少なくありません。しかし、その時間が不必要に長引いてしまうと、患者さんに「待たされている」「忘れられているのではないか」といった不快感や不信感を与えてしまいます。保留にする場合は、まず必ず「〇〇について確認いたしますので、少々お待ちいただけますでしょうか」と、理由と許可を得ることがマナーです。そして、保留時間はできるだけ短くするよう努めましょう。
一般的に、電話の保留時間は30秒から1分程度が限度とされています。それ以上長くなりそうな場合は、一度電話に戻り、「申し訳ございません、確認にもう少々お時間がかかりそうです。このままお待ちいただけますでしょうか。もしよろしければ、後ほどこちらから折り返しご連絡いたしましょうか」と、状況を説明し、相手の意向を確認する必要があります。たとえば、問い合わせ内容について担当者に確認が必要な際、担当者がすぐに見つからなかったり、他の電話に対応していたりすることがあります。
そのような状況で、ただひたすら患者さんを保留で待たせるのは避けるべきです。一度電話に戻り、「担当者がただ今他の電話に出ておりますので、終わり次第、こちらから折り返しご連絡させていただいてもよろしいでしょうか」と提案する方が親切です。折り返し連絡する場合も同様に、できるだけ迅速に対応することが重要です。「後ほどご連絡します」と伝えたにもかかわらず、何時間も連絡がなかったり、約束した時間を過ぎても連絡がなかったりすると、患者さんは非常に不安になります。
折り返し連絡をする際には、必ず「〇〇分後を目安にご連絡いたします」や「本日〇時までにはご連絡いたします」のように、具体的な目安時間を伝え、その時間を守るように最大限努力しましょう。もし、約束の時間までに連絡が難しいと分かった場合は、途中経過であっても一度連絡を入れ、「申し訳ございません、確認にまだ時間がかかっております。〇時頃には改めてご連絡できるかと思います」とお詫びと状況を伝える配慮が必要です。
たとえば、医師に確認が必要な件で、医師が診察中でなかなか捕まらない場合でも、「先生がまだ診察中のため、確認が取れておりません。終わり次第すぐに確認してご連絡しますので、もう少々お待ちいただけますでしょうか」と連絡を入れることで、患者さんは状況を理解し、安心することができます。待たせる時間を最小限に抑える努力と、こまめな状況報告が、信頼を損なわないための鍵となります。
感情的な対応や不適切な言葉遣い
医療機関には、様々な状況や感情を抱えた患者さんから電話がかかってきます。中には、強い口調でクレームを述べたり、理不尽な要求をしたりする方もいるかもしれません。しかし、どのような状況であっても、電話対応をするスタッフが感情的になったり、不適切な言葉遣いをしたりすることは絶対に避けなければなりません。感情的な対応は、問題をさらに悪化させ、医療機関全体の信頼を著しく損なう行為です。たとえば、患者さんから厳しい口調で不満を言われた際に、こちらもカッとなって反論したり、ため息をついたり、面倒くさそうな態度を示したりするのはNGです。
相手が興奮している場合でも、こちらは常に冷静さを保ち、まずは相手の言い分を傾聴する姿勢を示すことが重要です。「左様でございますか」「ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません」といった共感や謝罪の言葉を適切に用いながら、相手の感情を受け止めます。その上で、事実確認を行い、可能な範囲での解決策を提示するか、上司や担当者に相談するなどの対応をとります。また、不適切な言葉遣いにも注意が必要です。
丁寧語を使っていても、声のトーンや言い方によっては、冷たく突き放すような印象や、見下すような印象を与えてしまうことがあります。たとえば、「ですから、先ほども申し上げましたように」といった言い方は、相手を責めているように聞こえる可能性があります。「恐れ入りますが、再度ご説明させていただきますと」のような、より丁寧な表現を心がけましょう。さらに、患者さんに対して使うべきではない言葉もあります。たとえば、「できません」「無理です」といった否定的な言葉をいきなり使うのではなく、「あいにく〇〇はいたしかねますが、△△でしたら可能です」「ご希望に沿えず申し訳ございませんが、当院の決まりで〇〇となっております」のように、クッション言葉を使い、代替案や理由を添えて説明することが大切です。
親しい患者さんであっても、電話口では馴れ馴れしい言葉遣いやタメ口は避け、常に一定の距離感を保ったプロフェッショナルな対応を心がけるべきです。たとえば、いつも来院している患者さんからの電話でも、「あー、〇〇さんね、どうしたの?」といった対応ではなく、「〇〇様、いつもお世話になっております。本日はどのようなご用件でしょうか」と、丁寧に対応するのが基本です。感情のコントロールと適切な言葉遣いは、信頼される電話対応の根幹をなす要素と言えるでしょう。これらのNG対応を避けるためには、日々のトレーニングが欠かせません。次では、スキルアップのための具体的な実践方法についてご紹介します。
スキルアップのために:明日からできる実践トレーニング
ロールプレイングによる実践練習
電話対応スキルを向上させる上で、ロールプレイング(役割演技)は非常に効果的なトレーニング方法です。ロールプレイングでは、実際の電話対応で起こり得る様々な場面を想定し、スタッフが「患者役」と「対応者役」に分かれて、模擬的な電話のやり取りを行います。これにより、座学だけでは得られない実践的な感覚を養うことができます。たとえば、以下のようなシーンを設定してロールプレイングを行うことが考えられます。
- 新規患者からの予約受付
- 予約日時の変更依頼への対応
- 症状に関する問い合わせ(緊急性の低いもの・高いもの)
- 検査前の注意事項説明
- クレーム対応(待ち時間に対する不満、スタッフの態度への指摘など)
- 他の医療機関からの紹介患者に関する連絡
患者役は、様々なタイプの患者(例:高齢者、耳の遠い方、不安が強い方、怒っている方など)を演じ分けることで、対応者役は多様な状況への対応力を鍛えることができます。対応者役は、これまで学んだ基本的なマナーやシーン別の対応術を意識しながら、実際に声に出して対応してみます。ロールプレイングを行う際には、第三者の「観察役」を置くことも有効です。観察役は、対応者の言葉遣い、声のトーン、スピード、傾聴姿勢、情報の正確性などを客観的に評価し、具体的なフィードバックを行います。「声が少し小さく聞こえました」「代替案の提示がスムーズで良かったです」「専門用語を使わずに説明できていましたね」といった具体的な指摘は、対応者自身の気づきを促し、改善に繋がります。
たとえば、クレーム対応のロールプレイングを行った後、観察役から「相手の話を遮らずに最後まで聞けていた点は良かったですが、もう少し共感の言葉があると、相手の感情が和らいだかもしれません」といったフィードバックがあれば、次回の対応に活かすことができます。ロールプレイングは、定期的に、できれば様々なスタッフが参加して行うのが理想的です。他のスタッフの対応を見ることも、自身の学びとなります。最初は恥ずかしさもあるかもしれませんが、実践的なスキルを安全な環境で試せる貴重な機会と捉え、積極的に取り組みましょう。補足すると、実際の電話対応を録音し(患者さんの許可を得た上で)、後で聞き返して自己評価することも、ロールプレイングと同様に有効な学習方法です。
定期的な研修とフィードバックの機会
個々のスタッフの努力に加えて、組織として定期的な研修を実施し、フィードバックの機会を設けることも、電話対応全体の質を底上げするために重要です。研修では、電話マナーの基礎知識の再確認、新しい情報の共有(例:新しい予約システムの導入、変更された診療案内など)、最近あった事例の共有と対応策の検討などを行います。外部から専門の講師を招いて研修を行うことも、新しい視点や知識を得る良い機会となります。
たとえば、年に1〜2回程度の集合研修を実施し、電話対応の重要性や基本的なスキルについて改めて学ぶ機会を設けます。さらに、日常業務の中での短い勉強会やミーティングも有効です。たとえば、週に一度、数分程度の時間を使い、前週にあったヒヤリハット事例(クレームには至らなかったものの、問題がありそうだった対応)を共有し、どうすればより良い対応ができたかを話し合う場を設けるなどが考えられます。こうした機会を通じて、スタッフ全員が常に電話対応の品質向上を意識する文化を醸成することが大切です。
また、研修や勉強会と合わせて、上司や先輩スタッフからの定期的なフィードバックも欠かせません。日常の電話対応の様子を観察し、「〇〇さんの今日の対応、とても丁寧で分かりやすかったですよ」「△△の件、もう少し詳しく説明した方が患者さんは安心するかもしれませんね」といった具体的な声かけを行うことで、スタッフのモチベーション向上やスキル改善に繋がります。ただし、フィードバックは、単に欠点を指摘するだけでなく、良かった点を具体的に褒めること(ポジティブフィードバック)も重要です。
これにより、スタッフは自分の強みを認識し、自信を持って対応できるようになります。たとえば、新人スタッフが初めて難しい問い合わせに対応できた際に、「先ほどの〇〇様への対応、落ち着いていてとても良かったですよ。しっかり説明できていましたね」と具体的に伝えることで、本人の自信と成長意欲を高めることができます。組織全体で学び、互いにフィードバックし合う環境を作ることが、継続的なスキルアップを支える基盤となります。
応対品質向上のためのチェックリスト活用
日々の電話対応の品質を客観的に評価し、改善点を見つけるために、チェックリストを活用することも非常に有効な方法です。電話応対品質チェックリストには、基本的なマナーから具体的な対応内容まで、評価すべき項目をリストアップしておきます。スタッフは、このチェックリストを使って自己評価を行ったり、あるいは上司や同僚が対応をモニタリングして評価したりします。チェックリストの項目例としては、以下のようなものが考えられます。
- 【第一印象】3コール以内に応答できたか。明るくはっきりとした声で名乗れたか。
- 【言葉遣い】丁寧語・尊敬語・謙譲語を正しく使えていたか。専門用語を避け、分かりやすい言葉で説明できたか。
- 【聴く姿勢】相手の話を遮らずに最後まで聞けたか。適切な相槌を打てていたか。復唱確認を行えたか。
- 【話し方】聞き取りやすい声のトーンとスピードだったか。
- 【情報提供】質問に対して的確に回答できたか。必要な情報を漏れなく伝えられたか。代替案を提示できたか。
- 【保留・取次】保留前に断りを入れたか。保留時間は適切だったか。取り次ぎはスムーズだったか。
- 【クロージング】最後に不明点がないか確認したか。丁寧な挨拶で締めくくれたか。
- 【記録】メモは正確に取れていたか。
これらの項目について、「はい」「いいえ」「改善点あり」などで評価し、コメントを記入します。たとえば、自己評価で「専門用語を避け、分かりやすい言葉で説明できたか」の項目が「改善点あり」となった場合、「〇〇の件で、つい専門用語を使ってしまった。次回は△△と言い換えるように意識する」といった具体的な反省点と改善策を記録します。また、上司がモニタリングした際に、「保留前に断りを入れることが徹底できていて素晴らしいです。
ただ、保留時間が少し長くなる場合は、一度戻って状況を説明すると、より丁寧な印象になりますよ」といったフィードバックをコメントとして残すこともできます。チェックリストを定期的に活用することで、自分の強みや弱みを客観的に把握し、具体的な改善目標を設定することができます。また、チーム全体でチェックリストの評価結果を共有し(個人が特定されない形でも良い)、全体の傾向や課題を把握し、研修内容に反映させることも可能です。このように、チェックリストは、個人のスキルアップだけでなく、組織全体の応対品質向上にも貢献するツールとなります。これらのトレーニングを通じてスキルを磨き続けることが、最終的に患者さんからの信頼獲得に繋がります。
まとめ
この記事では、医療機関における電話対応の重要性から、基本的なマナー、シーン別の具体的な対応術、避けるべきNG対応、そしてスキルアップのためのトレーニング方法まで、幅広く解説してきました。顔が見えない電話だからこそ、一つひとつの言葉遣いや声のトーンが、患者さんの安心感や医療機関への信頼に直結します。受付スタッフや看護師の皆さんが、日々の電話対応において今回ご紹介したポイントを意識し、実践することで、患者満足度の向上、クリニックの評判向上、そしてスムーズな診療連携に貢献できるはずです。
特に、丁寧な傾聴、分かりやすい説明、迅速かつ正確な対応は、患者さんの不安を和らげ、信頼関係を築く上で不可欠な要素です。また、ロールプレイングや研修、チェックリストの活用といった継続的なスキルアップへの取り組みが、応対品質をさらに高める鍵となります。医療機関の「声の窓口」として、プロフェッショナル意識を持ち、常に相手の立場に立った温かい対応を心がけていきましょう。この記事が、皆さんの日々の電話対応業務の一助となり、より質の高い医療サービスの提供に繋がることを願っています。

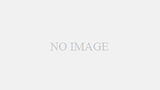
コメント