新社会人の皆さん、ご入社おめでとうございます。新しい環境でのスタート、期待とともに少しの不安もあるかもしれませんね。特にオフィスワークで避けては通れないのが「電話対応」です。学生時代にはあまり経験する機会がなかったかもしれませんし、「ちゃんとできるかな」「失礼がないかな」と心配になる方もいるのではないでしょうか。実は、電話対応は単なる取り次ぎ業務ではありません。会社の印象を左右し、お客様や取引先との良好な関係を築くための重要な第一歩なのです。この最初のステップでつまずかないためにも、基本的なマナーや手順をしっかり押さえておくことが大切です。
この記事では、新社会人の皆さんが自信を持って電話対応できるよう、基本のステップから好印象を与えるコツ、さらには陥りやすい注意点まで、具体的にお伝えしていきます。この記事を読めば、電話対応への不安が解消され、スムーズなビジネスコミュニケーションのスタートを切れるはずです。
ビジネスの第一歩 電話対応の重要性とは
会社の顔としての意識を持つ
電話に出るということは、あなたが会社の代表として、社外の人と接することを意味します。相手は、あなたの声や話し方、対応の仕方を通して、「この会社はどんな会社なのだろう」と判断します。たとえあなたが新入社員であっても、相手にとっては関係ありません。「〇〇社の△△さん」として認識されるのです。想像してみてください。あなたがどこかのお店に電話をかけたとき、非常に丁寧で明るい対応をされたら、そのお店自体に良い印象を持ちませんか。
逆に、ぶっきらぼうで要領を得ない対応をされたら、商品やサービスが良くても、少しがっかりしてしまうかもしれません。それと同じことが、あなたの会社の電話対応でも起こるのです。たとえば、あるお客様が製品に関する問い合わせで電話をしてきたとします。その際、あなたがハキハキと明るい声で「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社でございます」と応対し、丁寧な言葉遣いで用件を伺えば、お客様は「この会社は社員教育がしっかりしているな」と安心感を覚えるでしょう。
たとえその場で回答できない質問であっても、一生懸命に対応しようとする姿勢が伝われば、悪い印象にはなりません。逆に、面倒くさそうな声で「はい」とだけ答えたり、質問に対して「分かりません」と突き放すような言い方をしたりすれば、お客様は不快に思い、二度とこの会社とは関わりたくない、と感じるかもしれません。このように、電話口でのあなたの振る舞いは、そのまま会社の評価に直結します。常に「自分は会社の顔である」という意識を持って、責任ある対応を心がけることが大切です。新人のうちは慣れないかもしれませんが、この意識を持つことが、プロフェッショナルへの第一歩となるでしょう。
円滑なコミュニケーションの起点
電話は、ビジネスにおける様々なコミュニケーションの始まりとなることが多いです。お客様からの問い合わせ、取引先からの連絡、新しいビジネスチャンスにつながる提案など、その内容は多岐にわたります。電話対応がスムーズにいかないと、その後の業務全体に支障をきたす可能性があります。たとえば、取引先の担当者から、営業担当のAさん宛てに急ぎの連絡が入ったとします。電話を受けたあなたが、相手の社名や名前、用件を正確に聞き取れず、Aさんに曖昧な情報しか伝えられなかったらどうなるでしょうか。
Aさんは、状況がよく分からないまま折り返し連絡をすることになり、相手に再度同じ説明をさせてしまうかもしれません。これは、相手にとっても、Aさんにとっても時間のロスであり、場合によってはビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。逆に、あなたが相手の情報を正確に聞き取り、用件の緊急度を把握したうえで、「株式会社□□の△△様から、本日15時締切の見積もりの件で至急ご連絡ください、とのことです」とAさんに的確に伝えられれば、Aさんはすぐに対応でき、スムーズに業務を進めることができます。
このように、最初の電話対応が、その後のコミュニケーション全体の質とスピードを大きく左右するのです。また、社内の担当者への取り次ぎも重要な役割です。誰宛ての電話か、どのような用件かを素早く正確に把握し、適切な担当者へスムーズにつなぐことで、会社全体の業務効率を高めることにも貢献します。電話対応は、単なる受け答えではなく、組織全体のコミュニケーションを円滑にするための重要なハブ機能を持っていると言えるでしょう。したがって、正確なヒアリングと的確な伝達能力は、電話対応において非常に重要なスキルとなります。
信頼関係構築への影響
電話対応の質は、お客様や取引先との長期的な信頼関係を築く上でも、非常に大きな影響を与えます。丁寧で誠実な対応は、相手に安心感を与え、「この会社なら信頼できる」と感じてもらうための基礎となります。特に、初めて連絡を取る相手や、まだ関係性が浅い相手にとっては、電話対応がその後の関係性を左右する最初の関門となることも少なくありません。たとえば、ある企業が新しい仕入先を探していて、あなたの会社に初めて問い合わせの電話をしてきたとしましょう。
その際、あなたが親切かつ的確に対応し、相手の疑問や要望に丁寧に答えることができれば、「ここは対応がしっかりしているから、安心して取引ができそうだ」というポジティブな印象を与えることができます。これがきっかけで、大きな契約につながる可能性だってあるのです。反対に、ぞんざいな対応や不正確な情報提供をしてしまえば、たとえ製品やサービスが優れていたとしても、「この会社とはやり取りしたくない」と思われてしまうかもしれません。信頼は、一朝一夕に築けるものではありません。日々の小さなコミュニケーションの積み重ねによって、少しずつ育まれていくものです。
電話対応は、その積み重ねの重要な一部です。たとえ短い時間のやり取りであっても、相手への配慮を忘れず、誠意ある対応を心がけることが、結果的に会社全体の信用を高め、強固な信頼関係の構築へとつながっていきます。クレームの電話を受けた場合なども同様です。もちろん、クレーム対応は難しいものですが、まずはお客様の言い分を真摯に受け止め、丁寧に対応する姿勢を示すことが重要です。初期対応で誠意を見せることができれば、かえってお客様の信頼を得て、長期的なファンになってもらえるケースさえあります。このように、日々の電話一本一本が、会社の信頼という大切な資産を築き上げているということを忘れないでください。
このように、電話対応は会社の印象を決定づけ、円滑なコミュニケーションの起点となり、さらには信頼関係の構築にも深く関わる、非常に重要な業務です。では、具体的にどのように電話を受ければ良いのでしょうか。次のセクションでは、電話を受ける際の基本的なステップを詳しく見ていきましょう。
これで安心 電話を受ける際の基本ステップ
3コール以内での応答と適切な第一声
会社の電話が鳴ったら、できるだけ早く応答するのがマナーです。理想は「3コール以内」と言われています。なぜなら、電話をかけている相手を長く待たせるのは失礼にあたるからです。考えてみてください。あなたが誰かに電話をかけて、何回も呼び出し音が鳴り続けても誰も出なかったら、「忙しいのかな」「ちゃんと繋がるかな」と不安になりますよね。迅速な応答は、相手に「すぐに気づいてくれた」「待たされなかった」という安心感を与えるための第一歩です。もし、他の作業をしていてすぐに出られない場合でも、3コール以上鳴ってしまったら、「(大変)お待たせいたしました」という一言を添える心遣いが大切です。
さて、受話器を取ったら、次は何を言うべきでしょうか。これが「第一声」です。第一声は、明るく、はっきりとした声で、会社の印象を良くするように心がけましょう。一般的なフレーズとしては、「はい、〇〇株式会社でございます」や、「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社、△△(部署名)が承ります」などがあります。会社によっては、独自の決まった言い方がある場合もありますので、事前に先輩や上司に確認しておくと良いでしょう。ここで大切なのは、会社名を名乗ることです。これにより、相手は電話番号を間違えていないか確認できますし、あなたがその会社の人間であることを明確に伝えられます。
また、「ございます」という丁寧語を使うことで、相手への敬意を示します。たとえば、あなたが元気なく小さな声で「はい、〇〇です」とだけ言ったとしたら、相手は「本当に〇〇社かな」「なんだか頼りないな」と感じてしまうかもしれません。逆に、少し高めのトーンで、語尾まではっきりと「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社、営業部の山田が承ります」と言えば、相手は「しっかりした対応だな」と好印象を持つはずです。第一印象は非常に重要です。最初の3秒で、相手のあなた(そして会社)に対するイメージが決まるとも言われています。3コール以内の応答と、明るく丁寧な第一声。この二つを意識するだけで、電話対応のスタートは格段に良くなります。
相手の確認と用件の正確なヒアリング
第一声で好印象を与えたら、次は相手の情報を正確に把握するステップに移ります。誰から、誰宛てに、どのような用件で電話がかかってきたのかを正確に聞き取ることが、このステップの目的です。まず、相手が名乗ったら、その会社名と氏名を復唱して確認しましょう。「〇〇株式会社の△△様でいらっしゃいますね。いつもお世話になっております」のように、復唱することで聞き間違いを防ぎ、相手にも「ちゃんと聞いてもらえている」という安心感を与えることができます。
もし相手が名乗らなかった場合は、「恐れ入りますが、お名前と会社名を伺ってもよろしいでしょうか」と丁寧に尋ねましょう。次に、誰宛ての電話かを確認します。「〇〇(担当者名)はおりますでしょうか」と聞かれたら、その担当者が社内にいるかを確認します。もし担当者の名前が不明瞭だったり、聞き取れなかったりした場合は、「恐れ入ります、もう一度お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか」と遠慮なく聞き返しましょう。曖昧なまま取り次ぐのは、かえって失礼にあたります。そして、最も重要なのが用件のヒアリングです。
相手が何のために電話をしてきたのかを正確に理解する必要があります。用件を伺う際は、「どのようなご用件でしょうか」と尋ねます。話を聞きながら、必ずメモを取る習慣をつけましょう。メモを取る際には、「5W1H」(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識すると、情報の抜け漏れを防ぐことができます。特に、日時、場所、金額、固有名詞などは、聞き間違いやすいポイントなので、注意深く聞き取り、必要であれば復唱して確認します。「念のため復唱させていただきます。明日15時に、〇〇様が弊社にお越しになるということでよろしいでしょうか」といった具合です。
たとえば、ある取引先から「例の件で担当の佐藤さんに繋いでほしい」という電話があったとします。この「例の件」だけでは、佐藤さんは何の用件か分かりません。そこで、「恐れ入ります、佐藤に申し伝えますので、どのようなご用件か、差し支えなければお伺いしてもよろしいでしょうか」と具体的に尋ねる必要があります。「先日お送りした見積もりの件です」といった具体的な情報を引き出すことで、佐藤さんはスムーズに対応できます。正確なヒアリングは、その後の対応を円滑に進めるための鍵となります。焦らず、落ち着いて、相手の話に耳を傾けましょう。
保留・転送・終話時の丁寧な作法
相手の情報を確認し、用件をヒアリングしたら、次は担当者への取り次ぎや、電話の終了といったステップに進みます。ここでも、相手への配慮を忘れない丁寧な作法が求められます。まず、担当者に取り次ぐ場合や、何かを確認するために相手を待たせる必要がある場合は、「保留」機能を使います。保留にする前には、必ず「〇〇(担当者)に代わりますので、少々お待ちいただけますでしょうか」や、「確認いたしますので、少々お待ちください」のように、相手に一言断りを入れ、了承を得てから保留ボタンを押しましょう。
無言で保留にするのは失礼にあたります。保留時間は、長くても30秒から1分程度が目安です。それ以上かかりそうな場合は、一度保留を解除し、「申し訳ございません、もう少々お時間がかかりそうです。お待ちいただけますでしょうか」と状況を伝えるか、「確認後、こちらから折り返しお電話いたしましょうか」と提案するなどの配慮が必要です。受話器を手で押さえて「〇〇さーん」などと社内で呼びかけるのは、相手に聞こえてしまう可能性があり、マナー違反ですので絶対にやめましょう。
次に、担当者に電話を転送する場合です。担当者が電話に出たら、「〇〇株式会社の△△様から、~の件でお電話です」と、相手の会社名、氏名、簡単な用件を伝えてから転送します。これにより、担当者はスムーズに応対を開始できます。そして最後に、電話を終える際の作法です。用件が済んだら、「それでは、失礼いたします」や、「お電話ありがとうございました。失礼いたします」といった挨拶をして、電話を切ります。ここで注意したいのは、電話を切るタイミングです。原則として、電話はかけた側から先に切るのがマナーとされていますが、お客様や目上の方からの電話の場合は、相手が切ったのを確認してから、こちらも静かに受話器を置くのがより丁寧です。
受話器をガチャンと音を立てて置くのは、相手に不快感を与える可能性があるので避けましょう。たとえば、お客様からの問い合わせに対応し、問題が解決した場合、「他にご不明な点はございますでしょうか」と確認し、なければ「本日はお問い合わせいただき、ありがとうございました。失礼いたします」と丁寧に挨拶します。そして、相手が電話を切るのを少し待ってから、そっと受話器を置く。この一連の動作が、相手に最後まで良い印象を与えるためのポイントです。保留、転送、終話といった最後の瞬間まで、気を抜かずに丁寧な対応を心がけることが大切です。
これらの基本ステップをマスターすれば、電話を受けることへの不安はかなり軽減されるはずです。しかし、ビジネスでは電話を受けるだけでなく、こちらからかける場面も多くあります。そこで次のセクションでは、相手に好印象を与える電話のかけ方について解説します。
相手に好印象を与える 電話のかけ方
かける前の準備と心構え
電話をかける前に、少し立ち止まって準備をすることは、スムーズで効率的なコミュニケーションのために非常に重要です。いきなり電話をかけてしまうと、話している途中で「あれ、何を聞きたかったんだっけ」「あの資料どこだっけ」と慌ててしまい、相手に無駄な時間を使わせてしまうことになりかねません。まず、何のために電話をかけるのか、その目的(用件)を明確にしましょう。そして、伝えるべき内容、質問したいことなどを、事前にメモにまとめておくことを強くお勧めします。箇条書きにするだけでも構いません。
これにより、話の要点が整理され、伝え漏れや聞き忘れを防ぐことができます。たとえば、取引先に新しい企画の提案アポイントを取りたい場合、単に「アポ取りたいです」と電話するのではなく、「〇〇(企画名)について、△△様にご説明させていただきたく、30分ほどお時間を頂戴できないでしょうか。つきましては、来週の月曜日か火曜日の午後で、ご都合の良い時間帯はございますでしょうか」といった具体的な内容を準備しておくと、スムーズに話を進められます。
次に、話す内容に関連する資料やデータがあれば、手元に準備しておきましょう。相手から質問された際に、すぐに確認して答えられるようにしておくためです。ファイルを開いておく、該当ページに付箋を貼っておくなど、ちょっとした準備が、通話中のタイムロスを防ぎます。さらに、電話をかける時間帯にも配慮が必要です。相手の会社の始業直後(朝礼やメールチェックで忙しいことが多い)、昼休み(休憩中)、終業間際(帰り支度をしている可能性がある)などは、一般的に避けた方が良い時間帯とされています。もちろん、緊急の場合や、事前に相手の都合を確認している場合は別ですが、そうでなければ、相手が比較的落ち着いて対応できそうな時間帯(例えば、午前10時~11時半、午後1時半~4時頃)を選ぶのが無難でしょう。
もし相手の都合の良い時間帯が分かっているなら、それに合わせるのが最も親切です。そして最後に心構えです。電話をかけるということは、相手の時間を一時的に中断させることになります。「お忙しいところ失礼します」という気持ちを忘れずに、簡潔かつ丁寧に話すことを心がけましょう。これらの準備と心構えが、相手に「配慮のある人だな」という印象を与え、円滑なコミュニケーションの土台となります。
名乗りと用件を簡潔に伝える方法
さて、準備が整ったら、いよいよ電話をかけます。相手が出たら、まずはっきりと、そして丁寧に名乗ることが最初のステップです。「〇〇株式会社の△△と申します」のように、会社名と自分の氏名を伝えます。もし相手が不在で、別の方が電話に出た場合は、「〇〇株式会社の△△と申します。いつもお世話になっております。□□(部署名)の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか」というように、まず自分の身元を明かし、誰に取り次いでほしいのかを明確に伝えます。相手が目的の人に代わったら、改めて「〇〇株式会社の△△です。いつもお世話になっております」と挨拶し、名乗りましょう。
そして、相手が本人であることを確認したら、すぐに本題に入るのではなく、「ただ今、少々お時間よろしいでしょうか」と、相手の都合を尋ねる一言を添えるのがマナーです。もし相手が「今、ちょっと手が離せなくて」といった状況であれば、「かしこまりました。それでは、改めてお電話させていただきます。何時頃でしたらご都合よろしいでしょうか」などと、相手の状況を尊重する姿勢を示しましょう。相手の都合が確認できたら、いよいよ用件を伝えます。ここで大切なのは、「簡潔に、分かりやすく」伝えることです。事前に準備したメモを見ながら、まず「本日は、~の件でお電話いたしました」と、電話の目的を最初に述べましょう。
これにより、相手は何についての話なのかをすぐに理解でき、その後の話を聞く準備ができます。ダラダラと前置きが長くなったり、話があちこちに飛んだりすると、相手は何の話なのか分からず、ストレスを感じてしまいます。たとえば、「先日お送りした資料の件で、ご確認いただきたい点があり、お電話いたしました」のように、まず結論(目的)から話すことを意識しましょう。具体的な内容を説明する際も、要点を絞って、論理的に話すことが重要です。もし複数の用件がある場合は、「本日は2点、ご確認したいことがございまして…」のように、最初に伝えることで、相手も話の全体像を把握しやすくなります。名乗りから用件伝達まで、スムーズかつ手際よく行うことで、「この人は話が分かりやすいな」という印象を与えることができます。
相手への配慮を示す言葉選びと締めくくり
用件を伝える際には、言葉遣いにも細心の注意を払いましょう。丁寧語、尊敬語、謙譲語を適切に使い分けることはもちろんですが、それ以上に、相手への配慮を示す「クッション言葉」を効果的に使うことが、コミュニケーションを円滑にする上で役立ちます。クッション言葉とは、依頼や質問、反論などを切り出す前に添えることで、表現を和らげ、相手に与える心理的な負担を軽減する言葉のことです。たとえば、何かをお願いするときは、「恐れ入りますが」「お手数ですが」を前置きすることで、依頼のニュアンスが柔らかくなります。
「恐れ入りますが、〇〇の資料をメールでお送りいただけますでしょうか」。何かを尋ねるときは、「失礼ですが」「差し支えなければ」を使うと、唐突な印象を避けることができます。「差し支えなければ、〇〇様のご連絡先を伺ってもよろしいでしょうか」。相手の意見に同意できない場合や、断る必要がある場合も、「申し訳ございませんが」「あいにくですが」といった言葉を使うことで、角が立つのを防ぐことができます。「申し訳ございませんが、その日は既に別の予定が入っておりまして…」。
これらのクッション言葉を適切に使うことで、たとえ言いにくい内容であっても、相手への敬意を示し、良好な関係を保ちながらコミュニケーションをとることが可能になります。そして、用件が全て済んだら、電話を締めくくります。まず、「本日はお忙しいところ、ありがとうございました」と、時間を割いてもらったことへの感謝の気持ちを伝えましょう。最後に、「それでは、失礼いたします」と挨拶をして、電話を切ります。かける側から切るのが基本ですが、相手がお客様や目上の方の場合は、相手が切るのを待ってから、静かに受話器を置くのがより丁寧です。
たとえば、アポイントメントが取れた場合は、「それでは、来週月曜日の14時にお伺いいたします。本日はお忙しい中、ありがとうございました。失礼いたします」といった流れになります。最後の締めくくりまで丁寧に、相手への感謝と配慮を示すことで、電話全体の印象が格段に良くなります。言葉一つ一つに心を込めることが、相手に好印象を与えるための大切な要素です。
電話のかけ方にも、相手への配慮に基づいた様々な作法があることがお分かりいただけたかと思います。しかし、どんなに気をつけていても、うっかりミスをしてしまうことは誰にでもあるものです。そこで次では、電話対応で陥りやすいミスとその防止策について見ていきましょう。
陥りやすいミスを防ぐ 電話対応の注意点
言葉遣いと敬語の適切な使い方を学ぶ
電話対応において、言葉遣い、特に敬語の使い方は、相手に与える印象を大きく左右する重要な要素です。しかし、この敬語がなかなか厄介で、間違った使い方をしてしまいやすいポイントでもあります。新社会人が特に気をつけたい敬語の間違いをいくつか見ていきましょう。まずよくあるのが、尊敬語と謙譲語の混同です。尊敬語は相手や第三者の動作を高めて敬意を示す言葉(例:「いらっしゃる」「おっしゃる」「ご覧になる」)、謙譲語は自分や身内の動作をへりくだって相手への敬意を示す言葉(例:「伺う」「申し上げる」「拝見する」)です。
たとえば、お客様に対して自社の社長のことを話す際に、「社長がおっしゃっていました」と言うのは尊敬語で正しいですが、「社長が申し上げていました」と言うのは謙譲語なので間違いです。この場合は「社長が申しておりました」のように言います。逆に、お客様の動作に対して「〇〇様が申された件ですが」と言うのは間違いで、「〇〇様がおっしゃった件ですが」が正しい使い方です。社内の人間に対して社外の人のことを話す場合も注意が必要です。たとえば、上司に「〇〇社の△△様が参られました」と言うのは謙譲語「参る」を使っているので間違いです。
「〇〇社の△△様がいらっしゃいました」または「お見えになりました」のように尊敬語を使いましょう。また、「了解しました」という言葉も、ビジネスシーン、特に目上の方や社外の方に対して使うのは避けた方が無難です。「承知いたしました」や「かしこまりました」を使うようにしましょう。「了解」は同僚や部下に対して使う分には問題ありませんが、ややフランクな印象を与えるため、相手や状況を選ぶ言葉です。さらに、「~になります」という表現も、多用しすぎると稚拙な印象を与えることがあります。「こちら、お茶になります」ではなく「こちら、お茶でございます」、「料金は〇〇円になります」ではなく「料金は〇〇円でございます」のように言うのがより適切です。
「なる」は変化を表す言葉なので、元々そうであるものに対して使うのは厳密には正しくありません(例:「信号が赤になります」は正しい)。二重敬語にも注意が必要です。「〇〇様がお越しになられました」は、「来る」の尊敬語「お越しになる」に、さらに尊敬の助動詞「られる」がついた二重敬語です。「〇〇様がお越しになりました」で十分丁寧です。これらの敬語のルールは複雑に感じるかもしれませんが、基本を押さえて、意識して使うようにすれば、徐々に身についていきます。自信がない場合は、市販のビジネスマナー本で確認したり、先輩に尋ねたりするのも良いでしょう。正しい言葉遣いは、あなたの知性と信頼性を高める武器になります。
メモの取り方と復唱確認の徹底
電話対応において、聞き漏らしや聞き間違いは、後々大きなトラブルにつながりかねない重大なミスです。これを防ぐために不可欠なのが、「メモを取る習慣」と「復唱確認の徹底」です。「大丈夫、覚えているから」と記憶力に頼るのは禁物です。電話を切った瞬間に他の業務に気を取られたり、別の電話がかかってきたりして、肝心な内容を忘れてしまうことは、誰にでも起こり得ます。必ず、電話機のそばにメモ帳と筆記用具を常備しておき、電話を受けたらすぐにメモを取る習慣をつけましょう。では、具体的に何をメモすれば良いのでしょうか。基本は「5W1H」です。
- When(いつ):電話を受けた日時、相手が伝えた日時(例:明日の15時)
- Who(誰が):相手の会社名、部署名、氏名、連絡先
- Whom(誰に):電話を取り次ぐ相手(自社の担当者名)
- What(何を):用件、伝言内容
- Why(なぜ):用件の背景や理由(必要に応じて)
- How(どのように):相手が望んでいる対応(例:折り返し電話希望、資料送付希望など)
これらを意識してメモを取ることで、必要な情報を網羅的に記録できます。箇条書きで、キーワードを拾うように書くと、素早くメモが取れます。特に、数字(日時、電話番号、金額など)や固有名詞(会社名、氏名、商品名など)は、聞き間違いやすいポイントです。たとえば、「14時(じゅうよじ)」と「4時(よじ)」、「サイトウさん」の漢字(斉藤、斎藤、齋藤など)は、聞き間違いや勘違いが起こりやすい代表例です。こうした間違いを防ぐために有効なのが「復唱確認」です。聞き取った重要な情報は、必ず相手に繰り返して確認しましょう。
「念のため復唱させていただきます。〇〇株式会社のサイトウ様、漢字は斉藤様の『斉』でよろしいでしょうか」「お電話番号は、03-xxxx-xxxxでよろしいでしょうか」「明日14時(じゅうよじ)に、弊社までお越しいただけるとのことで、承知いたしました」といった具合です。復唱することで、もし聞き間違いがあった場合に、相手に訂正してもらうことができますし、相手にも「正確に伝わった」という安心感を与えることができます。メモを取り、それを声に出して確認する。この一手間が、ミスを防ぎ、確実な業務遂行につながります。面倒くさがらずに、徹底するように心がけましょう。
不在時の正確な伝言対応のポイント
電話をかけた相手(担当者)が不在の場合、その対応も電話を受けた人の重要な役割です。不在時の対応が不適切だと、相手に不快感を与えたり、重要な連絡が担当者に伝わらなかったりする可能性があります。正確かつ丁寧な伝言対応のポイントを押さえておきましょう。まず、担当者が不在であることを伝えます。その際、単に「〇〇は席を外しております」だけでなく、可能であれば不在の理由や状況を具体的に伝えると、相手は状況を理解しやすくなります。「申し訳ございません、〇〇はただ今、会議中でございます」「あいにく、〇〇は本日、外出しておりまして、終日社外におります」といった具合です。
ただし、プライベートな理由(通院など)の場合は、詳細を伝える必要はありません。「申し訳ございません、〇〇は本日、休暇をいただいております」のように伝えれば十分です。次に、いつ頃なら連絡が取れるかの見込みを伝えます。「会議は15時に終了予定ですので、その後連絡がつくかと存じます」「明日は通常通り出社予定でございます」のように、分かる範囲で構いませんので、目安を伝えられると親切です。もし戻り時間が不明な場合は、「戻り次第、こちらからご連絡いたしましょうか」と、折り返し連絡を提案しましょう。相手が伝言を希望された場合は、先ほど述べたメモの取り方(5W1H)と復唱確認を徹底し、正確に内容を記録します。
特に、「誰から」「誰へ」「いつ」「どんな用件で」「どうしてほしいか(折り返し電話希望か、メール連絡希望かなど)」を明確に記録することが重要です。相手の連絡先(電話番号)も忘れずに確認し、復唱しましょう。「かしこまりました。〇〇が戻りましたら、申し伝えます。念のため、ご連絡先のお電話番号を伺ってもよろしいでしょうか」のように尋ねます。折り返し連絡が必要な場合は、相手の都合の良い時間帯も確認しておくと、より丁寧です。「折り返しのお電話は、何時頃がよろしいでしょうか」。
記録した伝言メモは、担当者が確認しやすい方法で、確実に渡す必要があります。一般的には、伝言メモ用紙に記入し、担当者のデスクに置く、社内のチャットツールやメールで送る、などの方法があります。会社によってルールが決まっている場合が多いので、確認しておきましょう。メモを渡す際には、「〇〇様からお電話がありました」と口頭でも一言添えると、より確実です。たとえば、「先ほど、株式会社△△の□□様からお電話があり、本日17時までに折り返しお電話をいただきたいとのことです。
ご用件は、先日お送りした見積書の内容についてだそうです。ご連絡先は、伝言メモに記載しておきました」のように、口頭でも要点を伝えられると、担当者はすぐに行動に移せます。不在時の対応は、会社の連携プレーの見せ所でもあります。あなたが受けた電話を正確に担当者へつなぐことで、お客様や取引先からの信頼を守ることができるのです。
これらの注意点を意識することで、電話対応におけるミスは大幅に減らせるはずです。基本をしっかりと押さえた上で、さらに一歩進んだ対応を目指したいという方もいるでしょう。最後に、ワンランク上の電話対応を実現するための心得について触れていきます。
ワンランク上の対応を目指す プラスアルファの心得
聞き取りやすい声のトーンと話すスピードの調整
電話対応では、相手に顔が見えない分、「声」があなたの印象を決定づける非常に重要な要素となります。話の内容はもちろん大切ですが、その内容を伝える「声の質」も同じくらい、あるいはそれ以上に相手の受け取り方に影響を与えるのです。ワンランク上の対応を目指すなら、自分の声のトーンや話すスピードを意識的にコントロールするスキルを身につけましょう。まず「声のトーン」です。一般的に、少し高めの明るいトーンは、相手にポジティブで親しみやすい印象を与えます。
だからといって、常に高い声で話す必要はありません。大切なのは、状況に応じたトーンの使い分けです。たとえば、最初の挨拶「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社でございます」は、明るくハキハキとしたトーンで言うことで、会社の活気やウェルカムな雰囲気を伝えることができます。一方で、謝罪をする場面や、相手が困っている状況に共感を示す場面では、少しトーンを落とし、落ち着いた誠実な響きを意識すると、相手に気持ちが伝わりやすくなります。「申し訳ございません」という言葉も、明るいトーンで言ってしまうと、反省していないように聞こえてしまう可能性があります。声のトーンは、意識するだけで変えられます。
普段話す声よりも「ワントーン高く」を基本に、状況に応じて調整する練習をしてみましょう。次に「話すスピード」です。早口すぎると、相手は聞き取りにくく、せっかちな印象を与えてしまいます。逆に、遅すぎると、間延びしてしまい、相手をイライラさせてしまうかもしれません。理想的なのは、相手が聞き取りやすく、かつ内容を理解しやすい、適度なスピードです。具体的には、アナウンサーがニュースを読むスピードより、少しゆっくりめを意識すると良いでしょう。特に、会社名や氏名、電話番号、日時などの重要な情報を伝える際は、普段より意図的にゆっくり、はっきりと話すように心がけましょう。
相手が高齢の方や、電話口が騒がしい場所にいる場合などは、さらにゆっくり話す配慮も必要です。また、相手の話すスピードに合わせるというのも、高度なテクニックの一つです。相手がゆっくり話すタイプであればこちらも少しゆっくりめに、早口なタイプであれば少しテンポアップする(ただし聞き取りやすさは維持する)ことで、相手は心地よさを感じ、コミュニケーションがよりスムーズになることがあります。声のトーンとスピードは、練習すれば必ず上達します。自分の声を録音して聞いてみたり、同僚にフィードバックをもらったりするのも効果的です。「聞き取りやすいですね」「落ち着いていて安心感がありますね」と言われるような声を目指して、ぜひ意識してみてください。
クレーム電話への初期対応の基本
ビジネスにおいて、残念ながらクレームの電話を受けることもあります。お客様の怒りや不満を直接受け止めることになるため、多くの人が苦手意識を持つ対応かもしれません。しかし、クレーム対応こそ、会社の真価が問われる場面であり、適切に対応できれば、逆に顧客満足度を高め、ピンチをチャンスに変えることも可能です。新社会人の皆さんに、いきなり完璧なクレーム対応を求めるのは難しいかもしれませんが、初期対応の基本を知っておくことは非常に重要です。初期対応でまず大切なのは、「傾聴」と「共感」の姿勢です。
相手は、何らかの不満や怒りを感じて電話をしてきています。まずは、相手の言い分を遮らずに、最後までしっかりと聞くことに徹しましょう。「はい」「ええ」と相槌を打ちながら、相手が話しやすい雰囲気を作ります。相手の話を聞きながら、何に対して怒っているのか、何に困っているのか、事実関係を冷静に把握しようと努めます。感情的に反論したり、言い訳をしたりするのは絶対にNGです。相手の話が一通り終わったら、まずは不快な思いをさせてしまったことに対して、共感とお詫びの言葉を伝えます。「この度は、ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません」「〇〇の件でご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした」のように、何に対する謝罪なのかを明確にすると、より誠意が伝わります。
ただし、事実確認ができていない段階で、全面的に非を認めるような謝罪(例:「全面的に弊社の責任です」など)は避けましょう。あくまで、「不快な思いをさせたこと」「迷惑をかけたこと」に対して謝罪する、というスタンスです。次に、事実確認を行います。「恐れ入りますが、詳しく状況をお伺いしてもよろしいでしょうか」と丁寧に尋ね、5W1Hを意識しながら、具体的な状況をヒアリングします。ここでもメモは必須です。感情的になっている相手に対して、冷静に、しかし共感的な態度で質問を重ねていくことが求められます。
新入社員が自分だけでクレームを解決しようとするのは危険です。必ず上司や先輩に対応を相談しましょう。「申し訳ございません、私の一存では判断いたしかねますので、担当部署(または上司)に確認し、改めてご連絡させていただいてもよろしいでしょうか」のように伝え、相手の了承を得て、一旦電話を切るか、担当者に代わるのが一般的な流れです。その際、自分の名前と、折り返し連絡する場合の目安時間などを伝えると、相手は少し安心します。クレーム対応は精神的に負担が大きいですが、「お客様の声は改善のヒント」と捉え、冷静かつ誠実に対応する姿勢を身につけることが、ビジネスパーソンとしての成長につながります。
まとめ
今回は、新社会人の皆さんに向けて、ビジネスにおける電話対応の基本手順、好印象を与えるかけ方、注意点、そしてワンランク上の対応を目指すための心得について解説してきました。電話対応は、単なる作業ではなく、会社の顔としてお客様や取引先と接する重要なコミュニケーションです。最初は戸惑うことも多いかもしれませんが、基本をしっかり押さえ、一つ一つの対応を丁寧に行うことを心がければ、必ず自信を持ってできるようになります。3コール以内の応答、明るい第一声、正確なヒアリングと復唱確認、相手への配慮を忘れずに、かける前の準備を怠らないこと。
そして、もしミスをしてしまっても、そこから学び、次に活かす姿勢が大切です。この記事で紹介したステップや注意点を参考に、日々の業務の中で実践してみてください。電話対応スキルは、練習すればするほど上達します。そして、そのスキルは、あなたのビジネスキャリアにおいて、きっと大きな力となるはずです。自信を持って、ビジネスの第一歩を踏み出してください。

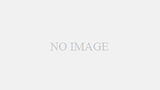
コメント